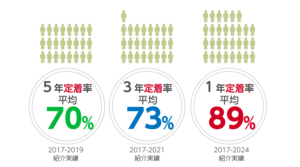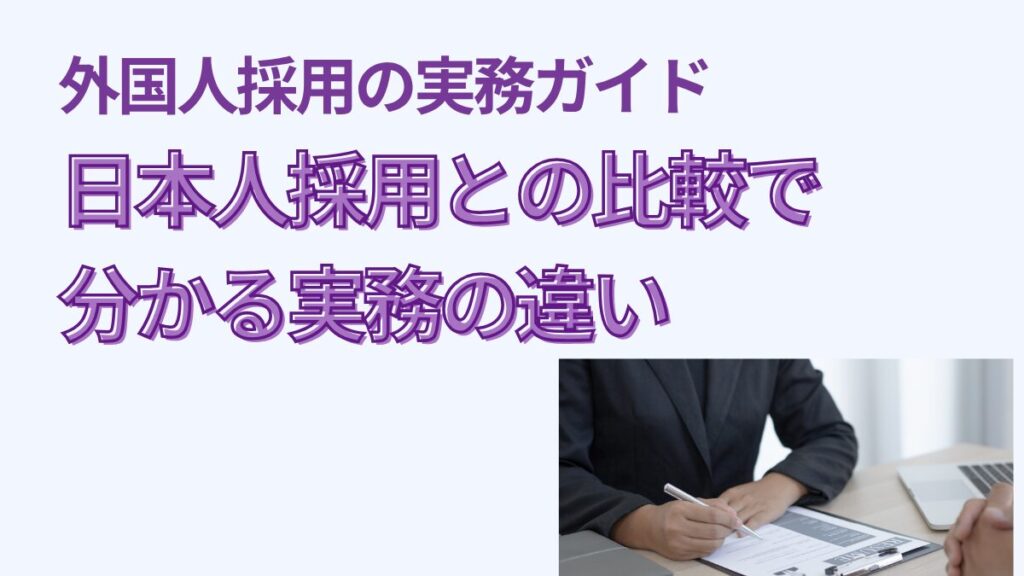
外国人採用では、ビザ取得などの複雑な手続きを踏まなければ雇うことができないことに加え、入社までの準備や生活面でのサポートなどを手助けしなければいけないというハードルがあります。外国人を雇用する前も、雇用した後も、採用担当者は外国人雇用に関する様々なやり取りの窓口になることが多いのです。
今回は、人事・総務の担当者必見の外国人採用の基礎知識をまとめます。
- 外国人を採用する場合と、日本人を採用する場合の人事担当者の負担を比較
- 外国人採用にかかる一般的な知識
外国人採用と日本人採用の比較
下表に、外国人採用と日本人採用で、採用ルートから入社手続き、社会保険や労働条件、生活サポートに至るまで、どのような違いがあるのかを一目で分かるように整理しました。事前に必要な準備や注意点を把握し、スムーズな採用活動や受け入れ体制の構築にご活用ください。
| 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|
| 採用ルート | 求人広告からの応募・直接紹介など | 外国人専門の人材会社からの紹介・海外の送り出し機関など |
| 入管法 | 適用なし | 入管法を守る必要がある |
| 在留資格 | なし | 在留資格の取得が必要 (定住者・永住者等を除く) |
| 就労制限 | なし | 在留資格により就労制限がある (定住者・永住者等を除く) |
| 働ける期間・雇用期間 | 雇用形態と契約期間による | 就労制限により働ける期間が決まっている (定住者・永住者等を除く) |
| 入社手続き | 原則本人がする | サポートが必要 |
| 役場手続き | 原則本人がする | サポートが必要 |
| 住居準備 | 原則本人がする | 会社で社宅を用意する場合がほとんど |
| 通勤手段 | 自動車・バイク・電車など | 自転車・徒歩通勤がほとんど |
| プライベート | 特別関与はしない | 生活のサポートも必要 |
| 社会保険 | 会社で加入 | 日本人と同じ手続きで加入 |
| 厚生年金 | 会社で加入 | 日本人と同じ手続きで加入 (※脱退一時金あり) |
| 雇用保険 | 会社で加入 | 日本人と同じ手続きで加入 (※外国人雇用状況の届出あり) |
| 給料 | 会社の賃金規定による | 日本人と同等以上 |
| 労働基準法 | 適用 | 日本人と同じように適用 |
| 保証人・緊急連絡先 | 国内の親族など | 国内にいない場合がほとんど (人材会社・支援会社などが緊急連絡先になる場合も) |
| 健康診断 | 実施方法は社内規定による | 日本人と同じ 通訳などサポートが必要な場合も |
| 年末調整 | 実施方法は社内規定による | 日本人と同じ 通訳などサポートが必要な場合も 海外の扶養家族に関する書類が必要 |
採用ルート
外国人の採用ルートは、留学生の新卒採用、国内転職、海外からの招聘、縁故採用があります。日本語を話せる外国人の場合は、企業の求人広告を見て応募するケースもあります。
- 留学生の新卒採用(ex.留学生のいる専門学校の就職課へ求人を出す)
- 国内転職(ex.外国人専門の紹介会社・派遣会社などへ求人を出す)
- 海外からの招聘(ex.海外の送り出し機関などへ求人を出す)
- 縁故採用
既に外国人を雇っている企業の場合、一番ハードルが低いのは、④縁故採用です。しかし、縁故採用は採用できる人数もタイミングも予測できません。そのため、安定して外国人採用ができるルートを開拓する必要があります。
外国人の日本への受入れに関わる業者は数多くあります。
業者を選ぶにあたり、最も一般的なルートは、
「知り合いで外国人材の斡旋をしているところに頼む」という方法ではないでしょうか。
知り合いがいない場合は、「インターネットで地元の業者を検索して探す」という方法もあります。
営業の電話やDMが会社に届く場合もあります。
海外の送り出し機関から直接営業の電話がかかってくる、ということもあります。
いずれのルートを選ぶにしても、外国人の採用担当者は、外国人の人事に関する情報を収集し、専門的な知識を身に付ける必要があります。正しい知識がなければ、悪徳業者に騙されてしまう可能性があるからです。
入管法
入管法を守る必要がある
日本に滞在する外国人全員に関わる重要な法律は、【出入国管理及び難民認定法】、通称【入管法】と呼ばれる法律です。外国人本人だけでなく、受入れる企業や機関も入管法を守る必要があります。守らなければ、”外国人受入れ停止処分”などの行政処分が行われてしまいます。
【出入国管理及び難民認定法】 出入国管理関係法令等 | 出入国在留管理庁
在留資格
在留資格とは
在留資格とは、外国人が長く日本に滞在するために取得する資格のことです。在留資格は日本に滞在する目的や期間を示します。在留資格がなければ、働くことも日本に住み続けることもできません。
働くことを目的とする在留資格の場合、受入れ企業が書類を準備し、海外から呼ぶ場合には申請を取り次ぐ必要があります。
在留資格の種類によって手続きの仕方や受入れできる外国人や企業の条件も異なります。
就労制限・働ける期間
「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「技能実習生」など「働くための在留資格」を持つ外国人には、働ける条件に制約があります!
就労制限とは
就労制限とは、外国人の在留資格によって、どのような仕事が認められているかを制限することです。
「定住者」「永住者」など身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人は、制限なしで仕事を行える一方、就労ビザを持つ外国人は、在留資格の範囲内でのみ仕事が認められています。
- 働ける場所(勤務先、所属など)の制限
- 働ける業種や職種の制限
- 働ける時間数の制限・・留学生のアルバイト週28時間など
- 通算で働ける期間の制限・・特定技能1号は通算5年など
※注:在留期限=働ける期間の制限ではありません!
例:「特定技能1号」→在留期限1年間を毎年更新します。
「技術・人文知識・国際業務」→1年、3年、5年の在留期限ですが、雇用契約がある限り通算で働ける期間の制限なく更新することができます。
入社手続き・役場手続き
サポートが必要
日本人の場合は、入社の際、「○○を持ってきてください」「○○の手続きをしてきてください」と指示するだけで良いですが、外国人の場合は企業や支援機関の人が付き添って役場の手続きに同行し、細かい手続きのサポートをすることが必要です。
- 市役所(区役所)での転居届
- 在留資格の取得に必要な「課税・納税証明書」などの書類をもらう手続き
- 銀行口座の開設
- 入社に必要な書類の準備や記入
住居準備・通勤手段
会社で社宅を用意する場合がほとんど
外国人を受け入れる際は、社宅の用意を検討する必要があります。
外国人がアパート契約を契約することは簡単ではありません。個人契約はもってのほか、法人契約でも「外国人入居お断り」という賃貸物件が数多くあります。
- 外国人がルールを守らないことが心配
- 日本人の保証人がいない
- 在留期限が短いから長期契約できない
といった理由で断られるケースが増えています。
社宅を用意する場合は、賃貸物件を法人契約し、家賃を給料から天引きします。
自転車通勤がほとんど
外国人は自動車免許を持っていない人が多いため、公共交通機関の少ない勤務先では、自転車通勤になることがほとんどです。自転車は会社で貸与する場合と、個人で買ってもらう場合があります。
プライベート
生活面のサポートも必要
人事担当者が日本人社員のプライベートや生活のサポートをするというのは稀ですが、外国人社員の場合、近くに知り合いやと友人もいない場合が多いので、会社や支援機関が生活面でのサポートをする場合がとても多いです。
- 交通事故に遭ってしまったとき
- 犯罪に巻き込まれたとき
- 訴えられたとき
- 帰国したら戻って来られなくなったとき
- 緊急で帰国したいとき
- 感染症にかかったとき
- 近所からのクレームを受けたとき
- 病気になったとき
- 自然災害が発生したとき
社会保険・厚生年金・雇用保険
外国人を採用した場合も、日本人と同じように厚生年金・健康保険・雇用保険に加入します。
※個人事業主が外国人を雇う場合も、外国人が国民保険に加入するため、役場でのサポートが必要です。
外国人は脱退一時金が適用
外国人が国に帰った場合、厚生年金や国民年金は、日本で納めた年金の一部を還付してもらう制度(脱退一時金)が適用されます。申請手続きが必要です。
外国人雇用状況の届出が必要
外国人が雇用保険に加入するとき、「外国人雇用状況の届出」も一緒にすることが義務付けられています。
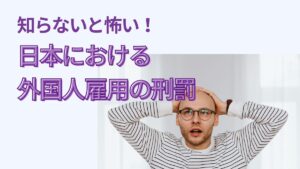
給料・労働基準法
給料は日本人と同等以上 労基法は日本人と同じように適用
外国人を雇用するときの条件や待遇は、日本人と同等以上というように決められています。給料は日本人社員と同じように、会社の賃金規定に従います。
また、労働基準法などの労働関係法令も、日本人と同じように適応されます。
以下は、ハローワークの「外国人の雇用に関するQ&A」の抜粋です。
日本国内で就労する限り国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。したがって、外国人にも日本人と同様に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等が適用されます。また、労働基準法第3条※は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。
参照:「外国人の雇用に 関するQ&A」令和7年発行【東京労働局職業安定部ハローワーク】
保証人・緊急連絡先
国内にいない場合がほとんど
外国人採用の怖いところとして、保証人や身内が国内にいないことが挙げられます。緊急連絡先は紹介してもらった人材会社や派遣会社になることも多いです。人材会社がしっかりしていれば、海外の身内の連絡先などを控えているので、いざとなったときに安心です。
健康診断
通訳などのサポートが必要な場合も
毎年の健康診断は外国人も受けなければなりません。簡単な日本語が話せる人は良いですが、診断書の記入などに通訳などのサポートが必要な場合もあります。
年末調整
通訳などのサポートが必要な場合も
外国人の年末調整は人事部や経理部の悩みの種でもあります。扶養家族として登録されている人が外国にいる場合、外国で発行される戸籍証明や送金記録などを一緒に提出しなければなりません。スムーズに年末調整を行うために、通訳などのサポートが必要な場合もあります。
まとめ
その他の人事についてのご質問にお答えします!
人事・総務の担当者必見の外国人採用の基礎知識をまとめましたが、上に挙げた以外に外国人の人事に関するご質問を、以下のフォームで受付しております。
外国人を受入れる企業の皆様のお役に立つ情報を随時更新していきたいと思います。
お気軽にお問合せください。